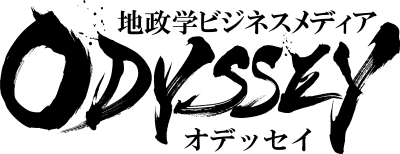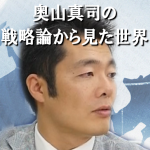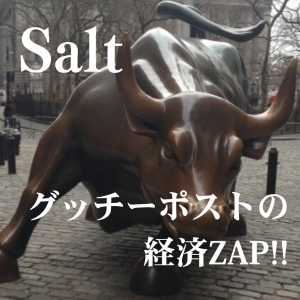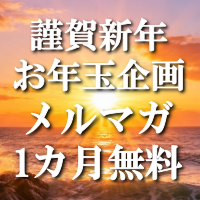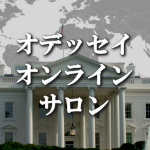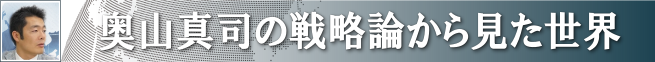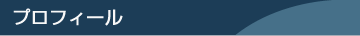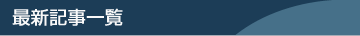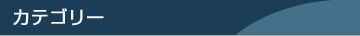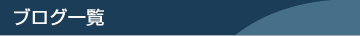2025/11/14 18:00 | 戦略論 | コメント(0)
ゲーム化する戦場
今週の戦略関連のニュースで注目すべきは、インドとパキスタンでのテロの応酬もありますが、高市首相が「存立危機事態」をめぐる国会答弁を行ったことで、三大地域(西欧、中東、東亜)の一角としての「東アジア」が熱気を帯びたことでしょう。
特に今回は、中国の在大阪総領事の暴言があり、それに端を発して、日米中を巻き込んだ国際問題に発展しているところが特筆に値します。
■【解説】 高市首相の台湾をめぐる発言、なぜ中国を怒らせたのか(11/12 BBC)
これについては、同総領事の発言が早々にSNS上で翻訳されて海外の識者やメディアに知れ渡ったことや、台湾メディアが積極的に取り上げたことによって、中国側も反応せざるを得なくなったという一面もあると思います。
しかし、北京側からみれば、何よりも、第二次大戦時の歴史的な経緯もあって、日本からの「宣戦布告」のように見えたというのも大きいのではないでしょうか。
一方、私としては「米中会談のあとに北京が強く反応した」という点に大きな意味があると考えております。なぜなら以下のように、トランプ大統領が、なぜか日本の高市政権側にあまり好意的ではない、実に渋い反応をしているからです。
■ 中国総領事の投稿 批判せず トランプ氏「同盟国も我々を利用した」(11/11 テレ朝NEWS)
これは邪推なのですが、おそらくトランプ大統領は今回の韓国での米中会談の実現のために習近平側にかなり譲歩したので、中国側に配慮したのではないかと思います。このため同盟国であるはずの日本に対してそっけない態度をとったと見ることもできます。
中国にしてみれば、アメリカと合意していたはずのこと(台湾問題には触れない)をその「属国」であったはずの日本の首相が覆してきたということが、なおさら気に食わなかったのかもしれません。
日本はこれまで、台湾有事に対しては存立危機事態をどのように認定するかについて、曖昧な態度を戦略的にとってきました。しかし図らずも立憲民主の岡田克也議員からの余計な質問で、「ついに明確な態度をとった」と見られてしまい、ハレーションが起こった、というのがいずれにしても実態だったように思います。
さて、今回の本題は、久々にウクライナです。同国はロシアに攻め込まれてすでに3年以上戦っているわけですが、その倫理的な問題は別として、戦略面で実にクリエイティブなことを行ってきました。そのことは、一部の業界ではよく知られた話です。今回はこの点を深堀りします。
※ここからはメルマガでの解説になります。目次は以下の通りです。
***********
ゲーム化する戦場
***********
▼ウクライナ軍の「ゲーム化」
▼ゲームとしての問題点
▼「究極のゲーム」?
***********
近況報告
***********
ゲームの話のついでですが、先週都内の某所でボードゲームの大会に参加してきました。
といっても、参加費は無料で、内容は超専門的です。実は民間の有志がシミュレーションゲームを教育などに活用している専門家を集めて行った、いわば「実験的」な催しでした。
使ったゲームは、アメリカの大手シンクタンクであるRAND研究所が作って2017年に発表した「ヘッジモニー」(Hedemony)という不思議な名前のボードゲームです。
サイトの説明によれば、同ゲームは「米国防衛専門家に対し、様々な戦略が、戦力開発・戦力管理・戦力態勢・戦力運用が交差するトレードオフ領域における主要な計画要因にどのように影響しうるかを教えるためのウォーゲーム」ということです。
お値段は日本円で5万円近くする高価で、市販されているとはいえ「専門家向き」というだけであってなかなか複雑であり、人数だけ集めて「よしやろうぜ!」とすぐにできるような代物ではありません。
しかもアメリカの政府高官向けなので、たとえば日本がそもそもプレイヤーとして想定されていません。しかし今回プレイする際に主催者の方々はあえて「日本陣営」を作ってプレイヤーに加えました。
1卓のプレイヤーは、全体のプレーをコントロールする「総裁部」が数人必要ですが、これに加え、アメリカ3人、中国2人、ロシア1人、EU/NATO1人、北朝鮮1人、イラン1人という構成になります。このため、およそ10数人が一つの卓(A卓)を囲み、別の部屋で同じ人数の卓(B卓)がプレイするという大掛かりなものになりました。
朝8時に集合して解散したのは夜の8時という12時間コース(!)だったわけですが、大学教授から現役の防衛省・自衛隊の高官たち、それにコンサル会社の社員やシンクタンクの人間など、議論のレベルが実に高く、あっという間の12時間でした。
私はA卓のEU/NATOを担当したわけですが、とにかく使える手が少ない。すぐとなりのロシアの脅威が迫っているのでその対処だけを考え、インド太平洋方面にはほとんど関心を持つことさえできませんでした。
もちろんこのようなゲームのシナリオが現実になるわけではないのですが、少なくとも自分の地域ではない別の地域のプレイヤーを担当することによって、その国の置かれた状況を実感できます。実に有益なものだとプレイするたびに毎度感じます。
全体として中国(もしくはレッドチーム)がかなり有利になりそうなところで時間切れで終了となったわけですが、多くのことが学べる質の高い(でも複雑な)戦略レベルのゲームであったと思いました。みなさんもチャンスがあればぜひ。
***********
好評発売中の書籍
***********
■『世界最強の地政学』文春新書(Amazonで期間限定で読み放題!)
■『新しい戦争の時代の戦略的思考』飛鳥新社
■『サクッとわかる ビジネス教養 新地政学』新星出版社、改訂版(再び増刷決定!)
■『やさしくわかるエネルギー地政学』小野﨑 正樹、技術評論社
■『クラウゼヴィッツ: 『戦争論』の思想』マイケル・ハワード著、勁草書房(増刷決定!)
■『地政学:地理と戦略』コリン・グレイ&ジェフリー・スローン編著、五月書房新社
■『戦争の未来』ローレンス・フリードマン著、中央公論新社
■『インド太平洋戦略の地政学』ローリー・メドカーフ著、芙蓉書房出版、
■『戦争はなくせるか』クリストファー・コーカー著、勁草書房
■『デンジャー・ゾーン』マイケル・ベックリー&ハル・ブランズ著、飛鳥新社
■『スパイと嘘』アレックス・ジョスキ著、飛鳥新社
■『アジア・ファースト』エルブリッジ・コルビー著、文春新書(第三刷決定!)
■『認知戦:悪意のSNS戦略』イタイ・ヨナト著、文春新書(★最新刊★)
当社に無断で複製または転送することは、著作権の侵害にあたります。民法の損害賠償責任に問われ、著作権法第119条により罰せられますのでご注意ください。
いただいたコメントは、チェックしたのち公開されますので、すぐには表示されません。
ご了承のうえ、ご利用ください。